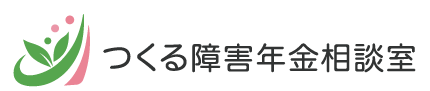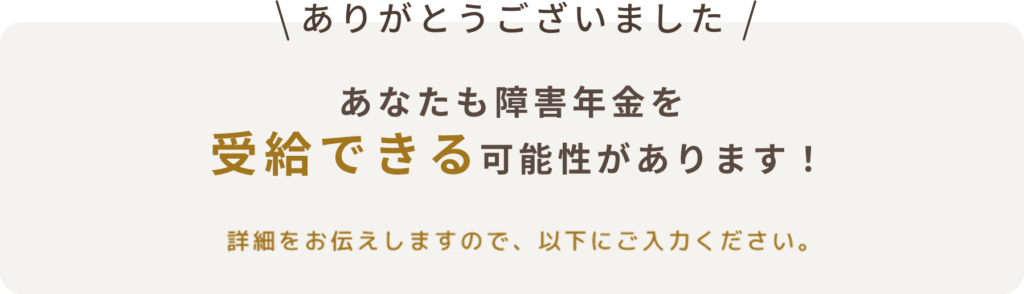今回は、
「どんなケガや病気が障害年金の対象になるか?」
「自分の病気やケガは障害年金の対象になるのか?」
という、多くの方から寄せられる疑問について、わかりやすくお答えしていきます。
どんな病気やケガが障害年金の対象?
障害年金は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。
病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神疾患、内臓などの内部障害も障害年金の対象になります。
主なものは次のとおりです。
1.外部障害
眼、聴覚、音声または言語機能、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
出典:日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/seido/shougai/shougai-kiso/20161114.html
これは例示であるため、ここになければ障害年金の対象にならない、というわけではありません。
他にも様々な傷病が対象となる可能性があります。
ですが、実は、障害年金の対象となるかどうかは、病名だけでは決まりません。
その病気やケガによって、日常生活や働くことにどの程度支障があるのかという「生活への影響度」も重要となります。
生活への影響度とは?
では、生活への影響度がどれほどのレベルであれば、障害年金の対象となるのでしょうか?
障害年金には、症状の重い順番に1級から3級まであり、その生活への影響度によって判断されます。
1級の目安
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできず、入院や在宅介護で常に介護が必要な状態です。
具体的にはこのような場合です。
・生活の範囲がベッド周辺に限られている
・常に援助が必要で、自力での身の回りの処理が困難
・一日中ベッドで過ごす必要があるなど、日常生活動作が著しく制限される
2級の目安
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの状態です。
具体的にはこのような場合です。
・生活の範囲が主に家の中に限られている
・ひとりで外出することが困難
・家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない、または制限されている
3級の目安
3級は、厚生年金加入期間中に初診日がある人のみが対象です。
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。
日常生活にはほとんど支障がなくても、労働については制限がある場合が該当します。
ただし、「ひとりで外出するのが困難」であれば2級、といったように機械的には判断されません。
障害年金の対象となるかどうかは、医師の診断書をはじめとした提出資料に基づき、総合的に審査されます。
専門家への相談がおすすめ
障害年金の認定基準は非常に複雑です。
障害年金を請求する際には、病名を伝えるだけではなく、その病気やケガによってどれほど日常生活に困っているかをしっかり伝える必要があります。
現在の症状が医師へ伝わらないと、症状が正確に反映された診断書とはなりません。
つまり、同じ病名でも、伝え方によっては、障害年金の請求結果が異なる可能性があるのです。
そのため、障害年金を請求する際には、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。
最後に
障害年金は、決して特別な人のための制度ではありません。
病気やケガで生活に支障がある方を社会全体で支えるための大切な制度です。
日常生活に困難さを感じられていたら、ぜひ一度専門家に相談してみてください。
以上、障害年金の対象となる傷病と症状について解説させていただきました。
少しでも皆様のお役に立てば幸いです。