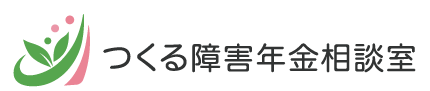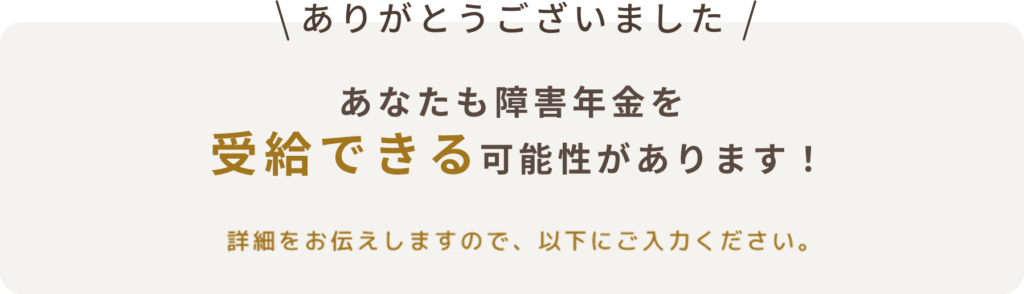はじめに
病気やけが、またはうつ病などの精神疾患で働けなくなったとき、生活を支える制度のひとつが「障害年金」です。
国民年金や厚生年金に加入していた人が、一定の障害状態になった場合に受け取れる公的年金で、老齢年金や遺族年金と並ぶ重要な年金制度の一つです。障害年金では、障害の重さに応じて1級・2級・3級と等級が定められ、その等級により年金額が決まります。ただし障害年金は(年金は)請求しないと受給することができず、また「いつ・どんな状態だったか」によって、請求の方法が異なります。
(障害年金は申請した誰もが受給できる年金ではありません。※詳細【解説】障害年金で大事な受給要件とは?)
原則は「障害認定日請求」ですが、条件を満たせば過去にさかのぼれる「遡及請求」や、現在の状態をもとにする「事後重症請求」という方法もあります。
今回はこの3つの請求方法について、それぞれの違いとポイントをわかりやすく整理してみたいと思います。
障害認定日請求(原則の方法)
障害年金の基本となるのが障害認定日請求です。
これは、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)において、障害の程度が障害等級に該当していた場合に行う請求方法です。
この場合、障害認定日の翌月から年金支給開始となります。
たとえば、病気やけがで長期療養していた方が、その認定日時点ですでに日常生活や就労に制限が生じている場合などが該当します。
遡及請求(さかのぼっての認定日請求)
本来、障害認定日の時点で障害等級に該当していたにもかかわらず、当時は請求をしていなかった場合に、後から認定日までさかのぼって請求する方法を「遡及請求」といいます。
たとえば、障害年金の制度を知らなかった、または経済的・心理的な負担が大きく当時請求できなかったといった理由で、時間が経ってから請求するケースです。
遡及請求の条件
遡及請求を成立させるには、次の条件を満たしている必要があります。
- 障害認定日時点で、障害年金の対象となる傷病であること
- 障害認定日時点で、障害等級に該当していたこと
- 認定日から3か月以内の症状をもとに作成された当時の診断書を提出できること
- 現在も障害等級に該当していること
通常、次の2種類の診断書を提出します。
① 障害認定日から3か月以内の診断書
② 請求日から3か月以内の診断書
もし①が準備できない場合は、原則として遡及請求はできません。その場合は、現在の状態に基づく「事後重症請求」を行うことになります。
ただし、認定日前後の診断書や医療記録などから当時の状態を確認できる場合は、遡及請求が認められるケースもあります。
遡及請求を行う際には、障害認定日当時の実態をできるだけ具体的に証明することが大切です。そのために定期的に病院に通うこと、病気やけがが重い時は、特に初診日から1年6か月(障害認定日)後あたりに診療を受けることは大切になってきます。
診断書のほかにも、
- 病歴・就労状況等申立書で当時の生活状況を詳しく記載する
- 出勤簿、タイムカード、休職通知などを添付する
家族や職場による当時の状況証明を補足するといった工夫で、より説得力のある申請書類を作ることができます。
障害年金の時効は5年
障害年金には5年の時効があります。
遡及請求が認められた場合でも、さかのぼって受け取れるのは過去5年分までとなります。
たとえば、障害認定日から7年後に請求を行った場合、2年分は時効により支給されず、残りの5年分が一時金としてまとめて支給されます。
実際に、過去分が認められて数百万円〜1,000万円近い額を受給できた例もあります。
事後重症請求(現在の状態で請求する方法)
一方で、障害認定日の時点では障害の程度が軽く、障害等級に該当していなかった場合でも、その後に状態が悪化したときは事後重症請求ができます。
この方法では、現在の障害の状態を示す診断書(請求日から3か月以内)を提出して請求します。注意点として、年金支給は請求書を受理された月の翌月分からとなり、過去にさかのぼっての受給はできません。
たとえば、認定日当時は通院や服薬で日常生活がある程度送れていたが、その後に症状が進行し、生活や仕事に支障をきたすようになった場合などが該当します。
まとめ
障害年金の請求方法は、「いつ・どのような状態であったか」によって請求方法が異なります。
認定日請求を基本としつつ、条件がそろえば遡及請求を、また現在の状態に応じて事後重症請求を検討することが重要です。
どの方法を選ぶかで、受け取れる年金額や支給時期が大きく変わることもあります。
「当時の診断書がないけれど、何か方法はあるの?」「どの請求方法で進めるべき?」
そんなときは、私たち社会保険労務士にご相談ください。 状況を丁寧に整理し、受給につながるよう申請をサポートいたします。