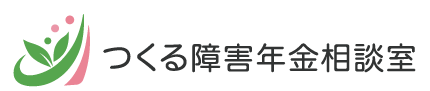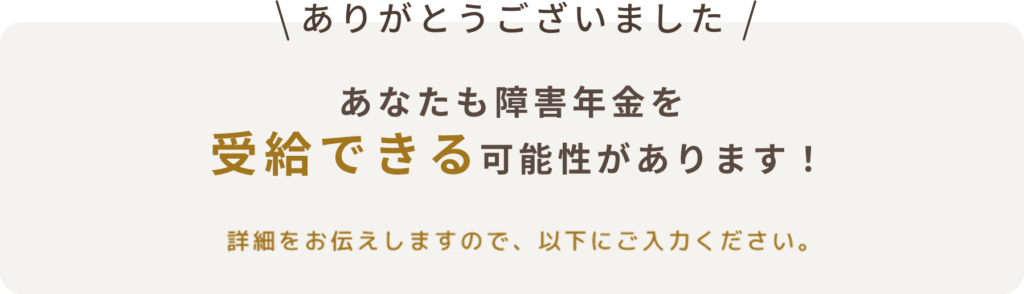「障害年金」とは、働き盛りの現役世代の方が病気やケガで働けなくなった場合、生活の支えとなる重要な制度です。
この記事では、障害年金の基本的な仕組みをわかりやすく解説していきます。
障害年金制度とは
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障がある方を支援するためのもので、国が運営している年金制度です。
一般的に「年金」というと高齢者向けのイメージがありますが、障害年金は20歳以上の現役世代の方でも受給できる制度です。
しかし、高齢者向けの老齢年金と異なり、必ずしも継続して支給されるわけではありません。
定期的に障害の状態について確認が入るため、障害の状態が改善され基準を満たさなくなれば、支援の必要なしとして支給が止まることもあります。
障害年金の仕組み
障害年金は、待っていれば自動的に支給される制度ではありません。
ご自身で請求手続きを行う必要があります。
ただし、請求すれば誰でも受給できるわけではなく、以下の3つの要件を満たす必要があります。
(1)初診日の時点で国民年金または厚生年金に加入していること
(20歳前、60~65歳で国内居住の方は加入していなくても国民年金の対象となります)
(2)年金保険料の納付要件を満たしていること
(3)障害等級表による障害の状態にあること
(1)の初診日に加入していたのが国民年金であれば、障害基礎年金が支給されます。
20歳前や国内居住の60歳~65歳で加入していない方も同様です。
加入していたのが厚生年金であれば、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、厚生年金の場合、障害厚生年金を受けられない程度の軽い障害でも、その症状が固定しもう良くならない場合は、一時金として障害手当金が支給されることもあります。
こちらは一時金なので、一度限りとなり、継続的には支給されません。
(3)の障害の状態が重い順から、障害基礎年金は1級、2級、障害厚生年金は1級、2級、3級と分類されます。
【参考】障害年金:日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
支給される金額
支給される金額は、障害の状態が重い順から高く、1級、2級、3級の順となります。
生計を維持している18歳未満の子がいる場合や配偶者がいる場合は、加算があるものもあります。
(1)障害基礎年金(昭和31年4月2日以降生まれの方)
1級:年額 1,020,000円(2級の1.25倍)
2級:年額 816,000円
※子の加算額があります:1人目・2人目各234,800円、3人目以降各78,300円
(2)障害厚生年金
厚生年金に加入していた間の給与額がもとになる「報酬比例部分」を用いて計算され、以下の率を乗じます。
1級:報酬比例部分の年金額の1.25倍
2級:報酬比例部分の年金額の1.00倍
※1,2級は配偶者の加算額があります:234,800円
3級:報酬比例部分の年金額の1.00倍 ※最低保障額あり:年額612,000円
(3)障害手当金(一時金)
報酬比例部分の年金額の2.00倍 ※最低保障額あり:年額1,224,000円
【参考】障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額:日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
【参考】障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額:日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
法定免除制度
障害年金は、20歳代や30歳代の方も対象となるため、本来ならばまだ国民年金保険料を払う対象となります。
ですが、障害基礎年金を受給している方は、支援が必要な状態であるということから、国民年金保険料が免除されることになっています。この制度は法律で決まっているので「法定免除」と呼びます。
ただし、この免除は強制ではありません。
将来を考え、国民年金保険料を払いたいという方は、払うこともできます。
【参考】国民年金保険料の法定免除制度:日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20140710.html
最後に
このように、障害年金制度は、病気やけがで日常生活や仕事が困難になった時に支えてくれる非常に頼りになる制度です。
ただし、申請は簡単ではありません。
日常生活や仕事の困難さを、申立書や診断書などの書類のみで表現する必要があるからです。
おひとりで頑張りすぎず、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。
早めの相談が、スムーズな受給につながります。