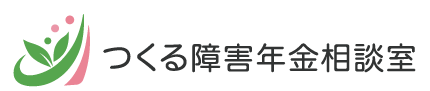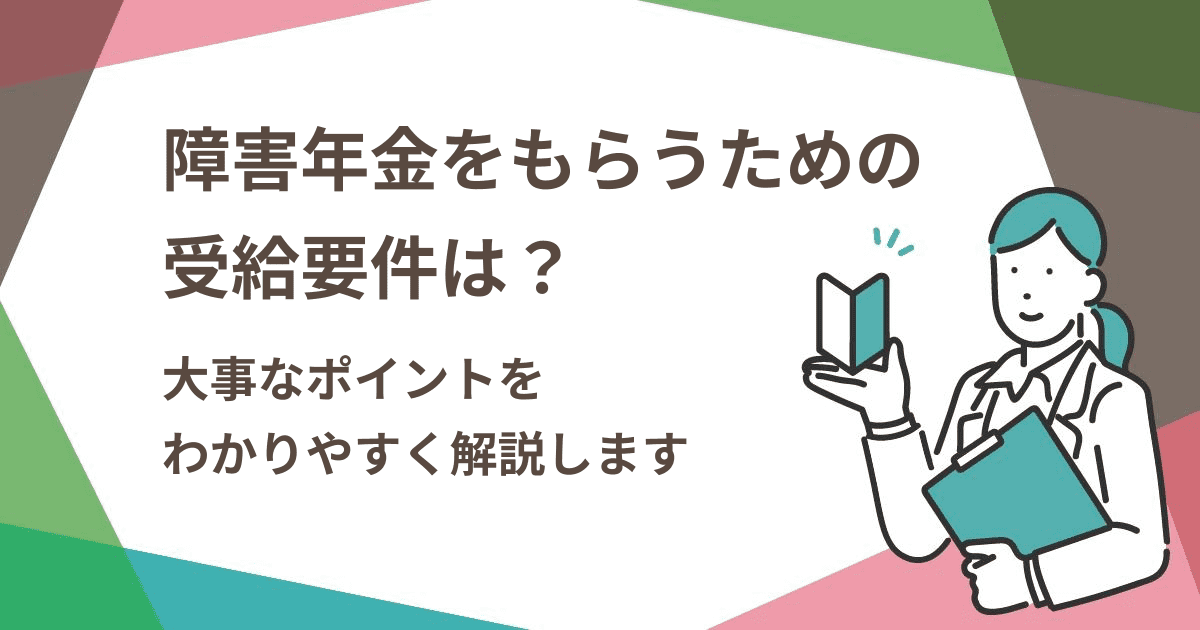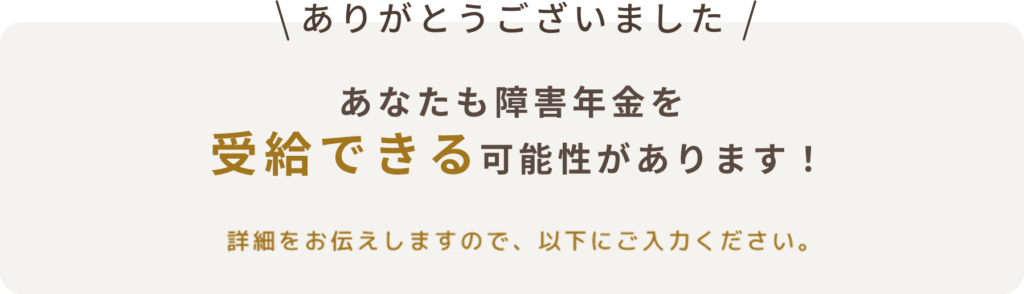「障害年金」とは病気やケガで働けなくなった場合、生活の支えとなる重要な国の制度です。
この記事では、障害年金の手続きについて順を追って解説していきます。障害年金申請のタイミングや、申請後の流れをつかんでおきましょう。
申請前に確認すること
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
(1)初診日要件
年金制度に加入している間に、初診日があること。
(2)保険料納付要件
初診日の前日において、一定以上の保険料納付済期間・保険料免除期間があること
(3)障害状態要件
障害認定日に法令で定められた障害の状態にあること
この要件を確認するのが、最初の大仕事です。
「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師や歯科医師の診療を受けた日のことです。
「障害認定日」とは、障害の状態を判断する基準となる日のことです。
「初診日」「障害認定日」は、障害年金が受けられるかどうかを左右する重要な日ですが、専門的な知識が必要な場合があるなど、非常に複雑です。
詳しくは、こちらのコラムで解説しています。
申請をするにはどうしたら良いのか?
障害年金は申請しないと受け取ることができません。申請手続きはご自身で行うか、専門家である社会保険労務士(社労士)に依頼する方法があります。
それぞれ、どんなメリットとデメリットがあるか、見てみましょう。
(1)ご自身で手続きする方法
年金事務所の窓口に相談しながら、ご自身で必要書類を収集し、申請書を作成します。
メリットは、ご自身で行うため、費用を抑えられることです。
デメリットは、
・病状が悪いときにもご自分で動く必要があり、負担が大きいこと
・日常生活で困っていることを、診断書を書く医師・歯科医師の先生に伝える大変さがあること
・専門用語が多く理解に時間がかかること
・書類の準備に手間取った場合、年金のもらい始めが遅くなる可能性があること
などがあります。
(2)社労士に依頼する方法
障害年金について専門的な知識を持つ社労士に依頼し、書類の収集から申請書の作成、年金事務所とのやり取りまで、代行してもらう方法です。
メリットは、
・ご自身の負担を大幅に軽減できるため、治療に専念できること
・障害年金の煩雑な手続きについて相談でき、不安を取り除くことができること
・専門的なアドバイスを受けることができるため、受給の可能性を高められること
デメリットは、費用がかかることです。
ご自身の病状や生活状況をもとに、手続きに時間がかけられるか、いくらなら費用負担が可能かなどを検討して、どちらの方法があっているか確認しましょう。
いつ申請すれば良いのか?
障害年金を申請する時期には、2つのタイミングがあります。
(1)障害認定日
障害の原因となった病気やケガについて、初診日から1年6か月経過した日、または症状が固定した日を基準にして、申請する方法です。
障害認定日に法令で定められた障害の状態にあることが認められれば、障害認定日の翌月から年金が支給されます。
申請が遅くなっても、認定日請求の場合は最大で5年遡って年金が支給される可能性があります。
(2)事後重症
障害認定日には受給できるほどの障害の状態ではなかったが、その後症状が悪化し障害等級の要件を満たした時に申請する方法です。
申請して認められた場合は、申請日の翌月分から年金が支給されます。
ただし、遡っての支給はないため、なるべく早く申請する必要があります。
(1)(2)どちらの場合も、申請書類の提出先は原則年金事務所になりますが、公務員の方はご自身が所属している共済組合となります。
申請の結果がわかるのはいつ?
書類を提出してから約3か月後に、結果が通知されます。場合によってはさらに時間がかかることもあります。
障害年金が認められれば「年金証書・年金決定通知書」が、認められない場合は「不支給決定通知書」等が届きます。
「年金証書・年金決定通知書」が届いた場合、最初の年金の振り込みは年金証書が届いてからおおむね50日後で、それまでの分がまとめて振り込まれます。
2回目以降は、偶数月の15日(15日が土日祝の場合は前倒し)に振り込まれます。
「不支給決定通知書」が届いた場合、不支給と決定された理由に不服がある場合は、通知書が届いてから3か月以内であれば、審査請求ができます。
まとめ
障害年金は、私たち現役世代が安心して生活を送るための大切な制度です。
しかし、制度の内容や手続きは複雑で、わかりにくい、難しい、と感じる方も多いかもしれません。病気やケガを抱えながらであれば、なおさらかと思います。
障害年金を請求したいが自分ではとてもできそうもないと思われた時には、ぜひ専門家にご相談ください。